


夏休みの土曜、日曜日に刈谷市総合運動公園で開催されるこの祭りは、テーマブースでの各種展示、いろいろな買い物が楽しめるびっくり横丁やフリーマーケット、子どもたちに人気の子ども広場、さまざまな催しのあるステージイベントが盛りだくさん。きっとお気に入りのイベントが見つかるはずです。そして日曜日にはスターマインを始めとする打ち上げ花火が真夏の夜空を彩る音と火の祭典を繰り広げます。
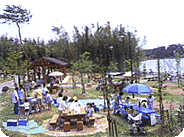
16haという広大な州原池を中心に温水プール、テニスコート、ロッジ、デイキャンプ広場、ファイヤー広場、愛知県刈谷勤労福祉会館などのスポーツ・宿泊施設が充実したレクリエーションゾーンとして整備された総合公園です。春は花見、夏はバーベキュー(要予約)、秋はKARIYA州原音楽祭、そして一年を通して水泳(大人300円、子人100円)にテニスと広く市民の憩いの場として親しまれています。
●州原温水プール
TEL:0566-36-8122 / 休館日:水曜日、年末年始

水野氏が天文2年(1533)に築城した刈谷城跡の本丸と二の丸の一部を利用した総合公園です。花見の名所として北部地区の州原公園と並ぶ刈谷市の2大スポットで、毎年春の3月下旬から4月上旬にわたって盛大に「桜まつり」が開催されます。公園内には各種会合、休憩所として利用される十朋亭があり、また、付近には体育館、刈谷球場、河川敷グラウンドなどのスポーツ施設も整っています。
刈谷市の最北部にある面積20,330平方メートルの小堤西池は、京都市大田の沢、鳥取県岩美町の唐川と並ぶ日本三大カキツバタ自生地の1つで、昭和13年に国の天然記念物に指定されました。花の見頃は、5月の中旬から下旬です。

江戸時代の5街道中、もっとも賑わった東海道は、江戸の日本橋から京三条大橋までの125里(491km)の街道です。江戸時代の紀行文には、池鯉鮒宿と鳴海宿の間にあった「立場」(たてば・茶屋の事)や名物「いも川うどん」のことが紹介されています。現在でも今川・今岡地内には当時の面影が残っています。

徳川家康の生母於大の方が岡崎の松平広忠から離縁された後、阿久比の久松俊勝と再嫁するまで住んでいたといわれています。平成10年度には東屋や於大の方の座像を配した庭園として新たに一帯を整備しました。
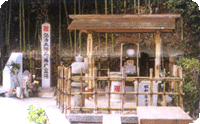
重原に乞井戸・佐次兵衛井戸・慕井戸と呼ばれる3つの井戸があります。弘法大師が重原に訪れた際、飲み水に困っている村人のために、祈って杖で土地に穴をあけると清水がこんこんと湧き出たという伝説があります。ここの井戸は佐次兵衛井戸で、乞井戸は重原本町、慕井戸は一色町にあります。各井戸に弘法大師の像がありましたが、現在は重原の浄福寺山門前の三ツ井戸弘法堂にまつられています。

土地は渡場とも書かれ、舟着場として利用されていた所です。この辺りには北浦と半崎の各土場が並んでおり、清水土場と併せて小垣江の土場といわれていました。江戸時代には衣ヶ浦の入江がこの辺りまで及んでいて、舟が着き、年貢米が積み出され、市原や高浜の湊で廻船に積み換えられ江戸に送られていました。この他、伊勢参りの人たちも、昭和初年頃までここから舟で出かけて行きました。常夜燈はその名残を示すものです。
大正末期から昭和初期の建築様式を留める亀城小学校旧本館を保存活用して、昭和55年に開館した資料館です。常設展示室には原始、古代〜中世、近世〜近代に分類された歴史資料、民俗資料が展示されています。また、建物が平成11年2月17日に国の登録文化財になりました。
TEL:0566-23-1488
休館日:月曜日、祝日の翌日、年末年始
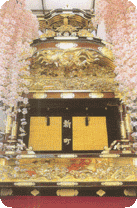
新町の山車
(市指定有形民俗文化財)
市原稲荷神社の祭礼に刈谷城下の各町内から奉仕された山車の1つで、新町のものです。
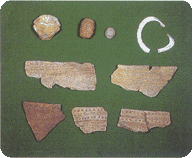
本刈谷貝塚出土品
(県指定有形文化財)
昭和44年に発掘調査された本刈谷貝塚から出土した縄文晩期の土製品、 石製品、骨角・貝製品、人骨など182点が展示されています。
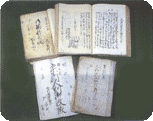
61万冊に及ぶ蔵書と幼児から高齢者まで気軽に利用できる設備を備え、貸し出しを中心に文献の収集、保存など情報センターとしての機能も充実しています。
TEL:0566-25-6000
休館日:月曜日、祝日の翌日、第4金曜日、年末年始
刈谷町方文書
(市指定有形文化財)
宝永7年(1710)から明治8年までの約160年間にわたって、刈谷町の庄屋が藩や幕府からの触書を克明に書き留めたものです。
村上文庫
(市指定有形文化財)
刈谷藩の御典医であった、村上忠順を中心とした村上家において、購入したものや筆写した書籍です。


